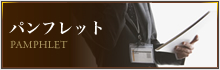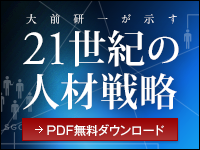塾生の声
答えのない時代にゆるぎない視座を求めて、大前研一の門を叩いた
次代のリーダーたちを紹介します。
プレジデント誌に掲載されたバックナンバーの記事を掲載しております。
本ページに掲載のプロフィールは、すべて取材当時のものです。
BBT経営塾体験記
-

日本のトップになれる思考法の身につけ方
石田 拓己
スターティアホールディングス
マーケティング部長 兼 クラウドサーカスCSO
1983年生まれ。博報堂、DMM、りらくを経て、2020年スターティアホールディングス入社。22年より現職。
インタビュー記事を読む -
大前研一さんが想像以上のスケールだった
石田拓己氏は現在、スターティアホールディングスのマーケティング部長と、クラウドサーカスの執行役員を兼務している。
「スターティアグループの各事業会社にある課題を分析・議論し、事業会社の一つであるクラウドサーカス社のプライシングなど戦略を立てる業務を行っています。重要なのは『生産性』の考え方です。たとえば、仕事そのものの意味や価値を議論し、その中で生成AIの技術が必要だと判断できたら技術を導入する。言葉や流行だけを追ってDX化やAI化を進めるのではなく、仕事の『生産性』を高めるために必要な要素を充実させていくイメージです」
議論の中で感じたある課題が、BBT経営塾の門を叩いたきっかけだった。
「これまで専門的に働いてきたマーケティング分野には自信がありました。しかし、ほかの分野は独学していたとはいえ書籍などから得た知識しかなく、自分の思考に軸がありませんでした。そうして、実務からの学びに限界を感じていたときに出合ったのがBBT経営塾です。ビジネスパーソンが直面する課題解決を繰り返し実践できて、その内容も現実の企業や社会情勢に基づき多岐にわたっています。トレーニングの中で視野が広がり、軸も見つけられるのではないかと思いました」
石田氏が話すBBT経営塾とは、数多くのトップマネジメントのコンサルティングを行う大前研一氏が塾長を務め、経営幹部や経営者にとって必要な広い視野と高い視座、戦略思考力、構想力を身につける1年間のオンライン講座の名称。カリキュラムは大前氏によって現在の日本企業の経営幹部にとって最重要なテーマが選定され、超実践的なプログラムとなっている。
講座の科目は合計5つで、3つの必須科目と2つの任意科目で構成されている。必須の3科目は、DXや脱炭素といった現代の日本企業にとって最重要なテーマで構成される「現代の経営戦略」。経営者として必要な論理思考から構想力までのスキルや思考力を磨く「新しい能力を身につける」。毎週一人の実在する企業の経営者を取り上げ、自分がその立場ならどうするかを考える「Real Time Online Case Study(RTOCS)」の3つ。任意の2科目は、塾長の大前氏が過去1週間の世界中のニュースについて独自の視点で解説する「大前研一ライブ」。そして企業経営者による「経営者講義」の2つとなっている。
講義はすべてオンラインで配信されるため、スマホやタブレット、PCとインターネット環境があれば受講できる。時間や場所を問わず受講が可能で、日本国内だけではなく海外在住の受講生も珍しくない。
講義の動画を視聴するだけの一方通行型ではない点もBBT経営塾の大きな特徴の一つ。プログラムではファシリテーターを交え、異業種のクラスメートと徹底的な議論を行うので、論理的に議論する力を磨きつつ視野も広げられる講座となっている。経営者や経営幹部候補生、将来経営者を目指す参加者も多いため、質の高い人脈形成が可能な点も特徴だろう。
石田氏はBBT経営塾で学び始めて間もなく、ほかのスクールやセミナーとの違いを感じたという。
「講義を行う大前研一さんの思考法やスケールの大きさに感銘を受けました。自分にはない視点で物事を見ていて、視野も広い。私たちが想像しているもっと上のレベルを見せてもらえました」
印象深いプログラムがあったという。
「『現代の経営戦略』の『あなたが独裁者だったら』というテーマの回です。何の独裁者かは指定されていなかったので、私は『日本の独裁者だったら』と仮定してレポートを提出しました。国をよくしようと一つの課題に対処するとほかが崩れてしまいます。それでも国を変えるためには、思い切った施策が必要です。そこで3つに絞って施策を提示しました。要約すれば地の利のある産業や観光、ロボットなどに注力する戦略ポートフォリオを組みました。こうして大きなスケールを持てたのは、大前さんの存在のおかげです」
石田氏は業務に加え、子どもを保育園へ送るなど平日は忙しく、土日に集中して課題をこなしていたという。
「受講生はオンライン上で文章で議論を行います。しかし、平日は朝から晩までなかなか時間が取れず、量より質で勝負するしかありませんでした。たとえば、土曜日の午前中の2時間半で課題を仕上げると決めて臨んでいました。もちろん家族の協力ありきですが、受講生から高い評価を得られることが多く、時間に制限があったことでかえって濃度の高いレポートが作成できていたのかもしれません。ちなみに、修了論文は5万字ほど書き、満点をいただいたのも嬉しかったです。かなり多いほうだと事務局の方から聞きましたが、読み返すと課題は感じるので、トレーニングを続けたいです」
-

長野から世界へ 視野が広がった理由
伊東 清美
八十二銀行
執行役員監査部長
1969年生まれ。92年八十二銀行入行。複数支店での支店長、人事部長を経て、2023年より現職
インタビュー記事を読む -
受講生とのやりとりで自信を取り戻した
長野県の地方銀行、八十二銀行に勤務する伊東清美氏。1992年の入行から2022年6月まで支店で営業職に従事していたが、本部に異動になり人事部長に、現在は監査部長のポストに就いている。経営塾への参加を決めたのも、この人事によるものだった。
「人事部長になって業務内容が大きく変わりました。それまで営業としてお客様と接して課題解決の提案をしていたところから、急に経営層と議論する機会が増えました。経験値がまったくありませんから、完全に自信喪失してしまったんです。『どうすれば自分の強みを確立できるのだろう』と調べて辿り着いたのがBBT経営塾でした」
伊東氏がBBTと接点を持つのは今回が初めてではないという。
「実は以前から新入行員研修でBBTを利用していたので、視野を広げてくれる充実したカリキュラムとクオリティの高さはすでに知っていました。加えて、以前『プレジデント』で取材されていた北國銀行の横越亜紀さんの存在も後押しになりました。横越さんも地銀の部長で女性。そんな方が『境遇が似ている方と入塾し共に学べることに魅力を感じました』とおっしゃっていました。私も部長として銀行を引っ張っていきたいと前向きになれました」
伊東氏は「『大前研一ライブ』から刺激を受けた」と話す。
「地銀で30年以上働いていると地域への目線が中心になり、思考が凝り固まってしまいがちです。大前ライブでは、大前さんが世界の情勢を独自の視点で解説してくれるので、柔軟に幅広く物事を見られるようになりました。受講生の皆さんも、私のつたない投稿に全力で反応してくれます。それ自体が自信となり、経営塾だけではなく、普段の会議でも議論に積極的になりました」
八十二銀行は26年に長野銀行と合併を予定している。長野県で最大規模の地方銀行になることについて、伊東氏が展望することとはなんだろうか。
「合併することで職員やステークホルダーも増えますが、あくまで地銀は地銀。地元のお客様とのコミュニケーションはおろそかにできません。そこをベースに、中国などアジアの市場と関わる機会が増えていくはずです。経営塾では、グローバルな視点で問題解決を実践する機会が得られました。その学びを業務に投入していきたいです」
経営幹部や経営者に向けたプログラムであるBBT経営塾だが、伊東氏は自身の経験から「もっといろんな人が学んでもいい」と話す。
「私は支店長から本部部長への昇進をきっかけに受講を始めて、マネジメントをするうえで必要な基礎スキルも身についたと思います。しかし、経営塾で学べる構想力や論理的思考力は誰もが仕事に活かせるはず。個人的には今後も働く期間が長い20~30代の若い方が受講するのもいいと思います」
-

世界の人材に伝わる雑談力とは
別所 貞雄
Kaneka Americas Holding,INC
R&B Manage
1985年生まれ。2010年カネカ入社。医療機器の研究開発および製造移管を経験し、20年より現職
インタビュー記事を読む -
専門にとどまらない大局が見えるようになった
カネカ・アメリカズホールディングに勤務し、シリコンバレーで医療機器の研究開発のほかに他社メーカーから技術を導入する業務に就いている別所貞雄氏。BBT経営塾を受講する決め手は、「雑談力のなさ」だという。
「私が働いているシリコンバレーにはさまざまな分野のプロフェッショナルが集まっていて、彼らと雑談になったとき、話題についていけないことが多かったんです。思えば大学生の頃、恩師から『君は〝専門バカ〟だ』と言われたことがありました。独学で書籍を読んではいましたが、結局それでは体験のないインプットが増えるだけ。自分から話題を提供するアウトプットの力が必要ですし、日常の雑談は信頼関係の構築にもつながります。BBT経営塾ならばアウトプットの実践に適していると思い、すぐに入塾しました」
受講開始後、第1回の「RTOCS」で別所氏は衝撃を受けたと話す。
「『RTOCS』のテーマに明確な答えはなく、初回のレポートは悩んだ末にとても複雑な提案をしました。しかし、大前さんはたった一枚のチャートで解説をしていた。私が行き詰まっていた部分も簡潔にまとめられていました。そこからは、一枚のチャートで一つのメッセージを明確に伝える提案を心がけました。修了する頃にはかなり身になっていたと思います。普段の業務でも、提案がズムーズに通ることが増えました。結果的に伝え方がうまくなり、雑談力の向上も感じています」
業種が異なるほかの受講生とのコミュニケーションも刺激になったという。
「研究職だとどうしても似たような人が周りに集まってしまいます。直感的だったり、ロジカルだったりと、いろんなタイプの人と交流することで自分の人間性も豊かになったと思います」
経営塾での学びや交流を通じて視野が広がった。その結果、医療機器業界の課題も見えたと別所氏は続ける。
「医療機器は治療に使いますが、将来的に予防医療が発展すると医療機器の需要が急速に縮小する日が来るかもしれません。医療機器メーカーは今後どのようにビジネスを展開するべきなのかは、業界全体の大きな課題だと思います。経営塾で学び大局を見られるようになったからこそ見えたものでした」
今回取材した3人は経営塾で学んだことで成長を実感できたと口を揃える。課題や目標という壁にぶち当たったとき、BBT経営塾は解決に向けての大きな力になるだろう。
-

経営者目線での決断をリアルに体感できる
宗澤 裕二
クラレ
ジェネスタ事業部 開発部 部長
1974年生まれ。99年、クラレ入社。耐熱性ポリアミド「ジェネスタ」の研究開発業務を経て、2009年より国内と欧州(ベルギー駐在)の市場開発業務を経験。23年より現職。
インタビュー記事を読む -
名経営者たちのように大胆なビジョンを描きたい
現在、クラレで耐熱性プラスチックの開発に部長として携わっている宗澤裕二氏。1999年の入社から開発部や営業部と歴任し海外営業の経験もある。経験豊富な宗澤氏だが、自身のさらなるステップアップのために「BBT経営塾」への入塾を決めたという。
「部長職についたあたりから、将来的には経営層を目指したいと考えるようになりました。しかし、自分にはまだそのために必要な視野の広さや視座の高さがありませんでした。経営層にはこれまでの経験では身につけられなかったさまざまなアプローチが求められるでしょうし、それらをOJT(オンザジョブトレーニング)で学ぶのもなかなか難しい。どうするべきか漠然と悩みを抱えていたときに、経営塾卒業生の上司から、経営層の考えが得られる場所だと聞いていたこともあり、『BBT経営塾』で学ぶ決意をしました」
そんなBBT経営塾で宗澤氏が最も熱中しているカリキュラムは、企業経営者の目線で問題解決に臨む、「Real Time Online Case Study(RTOCS)」だという。
「開発部の期間が長かったため、正直知識の少ない業界やテーマも多く、毎週頭を悩ませながら向き合っています。ですが、そのぶん経営層が苦悩して導き出す答えやその過程を自身の血肉にできているように思います。業界業種のまったく異なる受講生と議論をする中で、自分では考えもしなかった意見に感銘を受けることも多いです。自社以外の企業の歴史やそこから生まれる考え方を体験できており、『もし自分が経営者だったら』という思考がよりリアルなものになっています」
BBT経営塾で学ぶ中で、宗澤氏は経営者に必要なあることに気づいた。
「受講を通じて、企業が紡いできた歴史やビジョン、その歴史の中で一人一人の従業員が考えたことの大切さを痛感しました。それらを企業全体に浸透させていくことが、経営者の大切な仕事の一つなのだと思います。私自身、部長として開発部のメンバーに事業構想を伝える場面があります。そのときに、会社の諸先輩方が何十年も前から開発の基礎検討を始め今に繋いできた意味を踏まえ、どのように構想を伝えるべきかを考えるようになりました」
自身が描く経営者像もより具体的に見えてきたという。
「私が経営に携わるときには、小さなビジョンではなく、名経営者たちが見た大胆なビジョンを描きたい。そして、その世界観をメンバーに広め、日本だけではなくグローバルで輝ける会社を目指したいです。従業員だけでなく、関わってくれる人たち皆とディスカッションを重ねて成長できるといいですね。これは、BBT経営塾での議論が楽しい影響かもしれません」
-

地方から世界へ視野の拡大に役立つ
横越 亜紀
北國フィナンシャルホールディングス
常務執行役員 人材開発部長
1971年生まれ。94年北國銀行入行。個人営業、事務企画、デジタル部門等を経て2022年より現職。
インタビュー記事を読む -
「サザエさん見た?」のノリで講義が話題になる
石川県金沢市に本店をおく北國フィナンシャルホールディングス(北國FHD)の人材開発部長・横越亜紀氏。近年、北國FHDは企業全体でBBT経営塾へ積極的に取り組んでいる。
「北國FHDは地方銀行などを子会社に持つ企業です。近年は、コンサルティングや投資業務などと当社グループの役割も幅が広くなってきているため、従来のように銀行業務をこなせばいい状況ではなくなっています。そこで、幅広い人材の確保や能力の育成が必要と考え、リカレント教育やリスキリングに力を入れています。そういった方針もあり、BBT経営塾などの研修に参加するときは、会社から補助金を出し社員の学びを促進しています。私自身は以前から、別のBBTの講座を受講していましたが、経営塾は『経営者を目指す人のもの』と思って尻込みしていました。しかし、2022年3月から人材開発部長に就任しました。いわば教育の旗振り役です。今が好機と思い、前任も参加していた経営塾の門を叩きました」
日々の学びに刺激を受けていると話す横越氏だが、入塾してほどなくBBT職員から受けた、ある指摘が心に残っていると話す。
「『北國銀行さんの受講生は国際的な視点が欠けている方が多い――』。まさにそのとおりでした。弊社はもちろん北陸が拠点ではありますが、北陸だけではなく、日本全体、ひいては世界のことにも目を向けなければ、一企業としての成長はありえません。地方銀行の名前に甘え、視野が国内に限定されていたのではないかと反省しました。旗振り役として、企業全体の視野を広げていきたいですし、そこに経営塾の学びが大いに役立っています」
社員間の会話にもBBT経営塾の話題が上ることが少なくないという。
「日曜の夜に配信される『大前研一ライブ』は、月曜の共通の話題になることが多いです。世界のニュースを大前さんならではの視点で解説してもらえます。子どもたちが『昨日のサザエさん見た?』と話すように、ライブのテーマについて議論することも少なくありません。話題が共有できる仲間が周りにいることで学習に対する意欲も高まっています。企業としてBBTに参加しているメリットかもしれません」
横越氏はBBT経営塾の参加者について、「もっと多様性があってもいい」と話す。
「以前より、女性や40代以下の参加者は増えているようです。どんな方でも糧にできることばかりですし、20~30代の方もついていける内容だと参加者として自信を持って言えます。経営者を目指しているとか、起業したいという思いがなくても、現在の仕事には必ず活きるはずです。『経営塾』という名前に怖がらずに、ぜひ参加してみてください」
-

卒業生や同級生の縦横の繋がりを活かせる
上山 太一
NTT西日本
バリューデザイン部 コアソリューション部門長
1973年生まれ。96年にNTT入社後、法人向けビジネスや財界担当を経験。現職ではクラウドやデータセンター、SaaSやセキュリティ等におけるサービス開発に従事。
インタビュー記事を読む -
社内で自主的に「勉強会」を立ち上げた
NTT西日本に勤務する上山太一氏は、クラウド・セキュリティ・データセンター等のサービス開発の責任者を務めている。
「これまでも、中小企業診断士の資格を取得したり、BBT以外のセミナーを受講したりと、経営層に近い思考を身につける努力はしてきました。ただ、弊社グループの企業規模は大きく、実践の場があまり得られませんでした。BBT経営塾ならば、RTOCSのようなケーススタディで今までインプットしてきたノウハウを使うことができる。実践訓練でさらにスキルを磨くことができるのではないかと考えました」
上山氏は、BBT経営塾にかなりの情熱を注いでいる。そのモチベーションをこう語る。
「受講前に想定していた実践の場としての魅力はもちろんですが、何よりも受講生との議論が楽しく、学びが深められているからモチベーションが保てています。多くの受講生が言うように、他業種の同級生との会話の中で視野が広がり、自身のノウハウがブラッシュアップされていくのを感じます。また、オンライン上の関わりだけではなく、合宿でリアルな横の繋がりを築けました。定期的に勉強会や懇親会を開催していますし、さらには卒業生との会合もあり、経営層を経験した先輩方との縦の繋がりが得られたのも大きいです」
上山氏は自ら新たな取り組みを始めたそうだ。
「月に1回、社内で部下や若手の社員を募って勉強会を開催しています。テーマを設定し参加者で議論をして答えを導く、まさにRTOCSのようなイメージです。同僚と仕事以外の交流をもてますし、本業とは別のサークルのような集まりだからか、反応も上々です。なにより、勉強会を主催するようになって、自分の情報収集能力の未熟さを思い知らされました。同様の情報収集とアウトプットを毎週精度高く行っている大前塾長はさすがです」
取材場所に指定されたのは大阪・京橋にある『QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)』。今、NTT西日本が最も力を入れるオープンイノベーション施設だ。
「企業・個人・職業を問わず、さまざまな新規事業の共創や人材育成の支援の橋渡しを目指す場所です。たとえば、自社だけではなしえなかった事業を、外部のアイデアや人材を繋ぐことで実現させる。ビジネスにおけるインキュベーション(卵の孵化)を起こすための施設です。昨年3月オープンながら、10万人の方にご利用いただいています。BBT経営塾で得た知見を投入するとともに、人の繋がりを活かして新しいビジネスを生み出していきたいです」
-

年齢も役職も気にせず飛び込める
越野 恵里加
NEC
電波・誘導統括部 プロフェッショナル
1982年生まれ。2006年、NEC入社。通信企業向けITシステムの提案業務を経て、15年より航空管制関連システムの受注・戦略立案・提案業務に従事。21年より現職。
インタビュー記事を読む -
言語化力を高められる場所です
越野恵里加氏はNECの航空管制システムを開発・納入する部署で営業支援・事業戦略チームの管理職を務めている。取り扱うシステムには、飛行機が安全に運航できるよう管制官の判断をアシストするものなどがあり、より安全で効率的な運航に役立つという。
「飛行機が好きという想いで、現在の部署に2015年に異動し、21年4月から管理職に就きました。マネジメントをする立場になってか経営幹部と話す機会が増え、経営層に近い人たちがどのように思考しているのかに興味を持ったことが、BBT経営塾で学ぼうと思ったきっかけです。管理職という立場上、目の前の案件の問題解決やメンバーの育成・フォローに加え、事業拡大に向けた長期的な方向性を示してほしいと社内から期待されます。視野の拡大、視座の向上と併せて、今以上に相手に届くように伝えられる言語化力を磨く必要があると思いました」
これまでもほかのオンライン講座などを受講したことがあったという越野氏だが、BBT経営塾に入塾してもっとも意欲的に取り組んでいるのは「RealTimeOnlineCaseStudy(RTOCS)」だ。
「長期的な目線を持ち、言語化できるようになるためには、経営者の立場で議論ができるRTOCSがもっとも適していると受講前から考えていました。タイムリーなテーマについて、異業種のクラスメイトとディスカッションすると、思いもよらない方向から切り返されますし、私がなかなか言語化できないことを簡単に発言される方がいる。忖度なしの議論はとても刺激的です」
全編オンラインで受講できるBBT経営塾だが、コロナ禍では開催の難しかった、オフラインでの研修合宿や交流会も段階的に実施されている。
「合宿では、チームを組んでメンバーの一人が勤める企業のビジョンやバリューを2日かけて決めるワークがあります。同じグループには私よりも役職も経験も上の方が多く、グループディスカッションでは『そこに焦点を当てるのか』と驚かされてばかりでした。また合宿で交流した皆さんとLINEグループをつくっているのですが、世間話をしているところからふと仕事の話になり、 『じゃあ進めますか』と案件が決まることもあり、経営層の仕事のスピード感を体験できています」
塾生には経営者をはじめとしてエグゼクティブクラスの参加者も多い。ただ、 「興味があるなら年齢や役職を気にせず参加すべき」と越野氏は話す。
「やはり経験値が違うのでスキルや知識の差を感じる部分はあります。ただ、遠慮する場所ではないので、気楽に参加されればいいと思います。現在進行形で私が多くの学びを得られていますし、経験がまだ浅いとか、年齢が比較的若かったとしても、伸びしろがあると思えるのであれば、これほど恵まれた学びの場はありません。若い意見や考えも多様性のひとつ。少しでも興味があるならその気持ちを寝かせておくのはもったいないです。」
-

人ごとだった世界が自分ごとになる
中島 弘嗣
NTTデータビジネスブレインズ
社長
1973年生まれ。96年、NTTデータ入社。主に製造業界の顧客のシステムに携わり、2012年より大手飲料会社のIT子会社との資本提携後のビジネスを担当。21年6月より現職。
インタビュー記事を読む -
学びを自分にどう落とし込むか
中島弘嗣氏も、 「BBT経営塾に入塾して世界が広がった」と話す。中島氏が2021年6月から代表取締役を務め、日本板硝子に源流がある、NTTデータビジネスブレインズの主な業務は、情報システムの企画・開発・運用であるが、近年では時代の流れとともに自社開発のクラウドサービスにも力を入れているという。
「社長に就任して10カ月(当時)。経営者として日々の問題に対処できているとは思っていましたが、視野を広げる必要があると感じていました。同じNTTグループの同期や先輩で別会社の社長をしている人に相談しても、立場も環境も違うため、答えが得られない。自ら見つけるしかないと、 社内でも『参加してよかった』という声を多く聞くBBT経営塾の門を叩きました」
中島氏は「大前研一ライブ」を受講したことで「世界が広がった」という。
「大前さんの講義を聞いて、私の取り込む情報に偏りがあったと気付かされました。講義では、台湾有事や中国情勢、少子化など、いま起きている社会問題を取り上げています。もともと読書は好きでしたが、社会問題はどこか人ごとのように思ってしまっていて、あまり深掘りしてきませんでした。しかし、いざ学ぶと、限定された経営環境にある弊社においても、社会問題は身近なものだと気付きました」
「現代の経営戦略」も知識と思考を深めるために役立っていると続ける。
「台湾有事についてディスカッションを行ったとき、グループに中国籍の方がいて、我々とはまったく違う歴史観の意見をされていました。自分の常識は他人から見ると常識ではないこともある。お互いの国の常識に影響され、新しい世界の見方が生まれました」
合宿での経験も刺激的だったという。
「オンラインでの文字のやりとりだとじっくり考えて発言できますが、対面での話し合いになるとやはり会話が弾みます。ビジョンやバリューを話し合っているうちに、本当の社員同士のような感覚になりました。BBT経営塾では、学びを自分に落とし込んでどう活かすかを考える必要があると思います。台湾有事での議論がいい例で、正解もルールもありませんし、大前さんの意見も絶対ではないと個人的には思っています。インプットは大切ですが、学んだことを自分に落とし込んでどう活かすか。そこがBBT経営塾で得られた一番大きな学びかもしれません」
-

経営塾が培ってきた「共有財産」に触れる
倉光 正夫
ニフコセントラルメキシコ
拠点長
1980年生まれ。2005年、ニフコ入社。商品設計、重要保安部品の生産準備業務を経て、スペイン、メキシコにて海外実務を経験。2018年より現職。
インタビュー記事を読む -
経営者としてブレない心を獲得したかった
ニフコセントラルメキシコの拠点長である倉光正夫氏はBBT経営塾で「答え合わせ」をしているという。
「メキシコに拠点長、いわば社長として赴任したのが2018年。最初の2年は失敗ばかりで経営も悪化し、どん底の状態でした。トップの仕事である経営判断の際も不安と孤独感にさいなまれていました。それでも、責任を負う一国一城の主という思いが強く、 『俺が決めたことに従え』という思いが言動に出ていたと思います。そんな折、会社からBBT経営塾への参加を勧められたのですが、一度断っています。経営塾の存在とクオリティの高さは知っていたものの、打診されたのが迷走している真っただ中で、自分にまったく余裕がなかった。せっかく受講するなら時間をかけて向き合えるようになってからと考えていました」
その後、自身の考え方やふるまいを改め、社長業と業績も復調した。 「いまなら腰を据えて受講できる」とBBT経営塾に参加した。
「経営塾には、ブレない心の獲得を目的に入塾しました。経営者の資質として社長就任後2年で味わった不安感と孤独感の克服が必要だと、身をもって感じていました。また、失敗から再起できた自分の思考は正しいのか答え合わせをしたかった。実際、講義内容や議論から自身の考えや行動の一個一個を振り返ることができたうえ、自分がいかに恵まれているかを実感しました」
倉光氏が印象的だと語るカリキュラムは「新しい能力を身につける」だ。
「質問する力、考える力、議論する力を磨くことができ、人間性の向上に繋がっている。畑違いの同期生の視点や考えを自分にフィードバックするいい機会になっています。同期生には課長や部長クラスが多く、議論の中ではかつて自分が悩んでいたことにたびたび遭遇します。議論し意見しながら、自分の考え方や意識は正しかったのかを答え合わせしています。思考を文章化してオンラインで議論するシステムも面白い。文章化という段階を挟むことで、自分の思考を整理できますし、多くの人の思考のログを集積できます」
倉光氏が受講に際し大切にしているのは、人間性だという。
「どん底の時代は、すべて自分が決定しなくてはならないと思い込んでいました。しかし、専門的な仕事はスペシャリストに任せるほうが絶対にいい。では経営者の仕事は何かというと、優秀な人材を惹きつける器の大きな人物になることです。人間性が出来上がっていれば優秀な人材は寄ってきます。自身の成長のために、経営塾での学びには一カ月で60時間以上はかけています。もちろん、かなり多いほうだとは思いますが、BBT経営塾の魅力のひとつによく挙げられる『集合知』は、私からすると『共有財産』です。共有財産に触れられるかけがえのない体験があるからこそ、ライフワークのように没頭しているのだと思います」
これから経営者を目指す人、経営をしながら迷う人、挫折を乗り越えて経営の正解を確認する人、BBT経営塾はどんなビジネスパーソンにも気付きと学びが得られる場なのだろう。
-

集積された「知」が経営塾の魅力
澤原 英則
横河電機
U.S. Technology Center
Principal Architect, Evangelist
2004年、横河電機入社。エッジ制御装置の企画、開発、販売を経て、19年より米国でオープンイノベーションによる次世代プラント制御の国際標準化、R&Dに従事。
インタビュー記事を読む -
経営力は継続で身につけられる
澤原英則氏は横河電機のアメリカ現地法人に赴任しており、テキサス州在住だ。オイル&ガス、化学、医薬、再生可能エネルギーといった主に流体や気体を扱うプロセス産業において、生産を行うプラント・工場の自動化システムの研究開発やマーケティングに従事している。
「それらの事業におけるこれまでのやり方に加えて、現在は特定企業の独自技術で構成されたシステムに依存してしまう『ベンダーロックイン』からの脱却に向け、世界共通でオープンな制御システムをつくる国際標準化活動にもかかわっています。そうした標準化のためには、IT技術、オペレーションテクノロジー、エンジニアリングテクノロジーといったものを、弊社の力だけではなく他社と協力して融合させていくオープンイノベーションが必要だと強く感じていました。そんなときに、会社から経営塾への参加を打診されました」
「これまでのキャリアでバランスシートや損益計算書に責任を持つといった経営的な役職を経験していないので、今後のキャリアで必要になってくる経営能力やその適性に課題を感じていました。そんなときに『経営塾』という名前を聞き、自分の弱さを見つめ直して、経営に対する戦闘力を上げるチャンスだと思って入塾を決めました」
米国にいながら、オンラインで受講可能なため時間と場所を選ばなくてもいいことや、自身が抱えていた課題の解決に役立つかもしれないという思いから経営塾の門を叩いた。
「以前『経営塾』に参加した同僚から、ただの座学ではなく、いろいろな企業の上層部の方が集まって活発に議論ができる場だと聞いていました。入塾してみると、その充実感は想像以上でした。日本の社会問題や世界の潮流、教育、経済、金融、ファイナンスやテクノロジーなど、幅広い分野をテーマに課題が出され、それに基づいた議論が徹底的に行われます。考えもしなかったことを思考することになるので、視座が高まり構想力が磨かれるだけでなく、脳の使っていなかった部分が刺激されました」
澤原氏が経営塾を語るポイントのひとつに「集合知」があるという。
「立場も職種も違うクラスメイトとさまざまな角度で議論をすることができました。その経験の最たるものが『RTOCS』です。多種多様な企業の分析、本質的課題の特定、戦略構築を、同期生と議論しながら集合知で導き出していくことが楽しく、毎週欠かさず参加していました。この集積した知こそが経営塾の魅力だと思います」
入塾当初から講座に積極的に取り組んでいた澤原氏。あるとき、自身にポジティブな変化が表れたという。
「経営力は才能ではなく、継続することで間違いなく身につけられるものなのだと気づきました。課題を毎週筋トレのように続けていると、あるとき、企業の有価証券報告書等をざっと眺めるだけで本質的課題を解決するために何が必要かをざっくりと導けるようになっていたんです。過去に出てきた企業や他産業の成功事例をもとに、参加当初から自分なりのフォーマットで企業分析ドキュメントをつくっていたことも大きな力になったと思います」